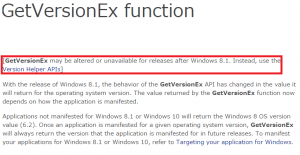クライアントプログラムをコマンドラインパラメータでシステムを切り変えるシステムの
重複起動防止処理のサンプル。
続きを読む
カテゴリー別アーカイブ: IT全般
oracle 既存オブジェクトへの上書き
既存のオブジェクトに対してimportするときに、新規インポートと同様にするとエラーが発生する。
そこで下記オプションをつけることで、上書き可能となります。
ignore=y
シャットダウンのサンプル
UNDO領域縮小
環境にあわせて読み替えて下さい。
・現在 UNDOTBS1
確認方法は以下
SELECT SEGMENT_NAME, OWNER, TABLESPACE_NAME, STATUS FROM DBA_ROLLBACK_SEGS;
・一時退避領域作成
create undo tablespace UNDOTBS2 datafile ‘C:\app\Administrator\oradata\サービス名/undotbs02.dbf’ size 10m;
・紐づけ
alter system set undo_tablespace = ‘UNDOTBS2′;
・削除、再作成
drop tablespace UNDOTBS1;
create undo tablespace UNDOTBS1 datafile ‘C:\app\Administrator\oradata\サービス名\undotbs01.dbf’ size 100m reuse autoextend off;
alter system set undo_tablespace = ‘UNDOTBS1′;
・削除
drop tablespace UNDOTBS02 including contents cascade constraints;
・確認
SELECT SEGMENT_NAME, OWNER, TABLESPACE_NAME, STATUS FROM DBA_ROLLBACK_SEGS;
データファイルの作成方法
ユーザを作成する際に、データファイルとの紐づけが必要です。
作成方法は以下で、下記コマンドを実行すると初期サイズ100MBで自動拡長のデータファイルが作成されます。
CREATE TABLESPACE
スキーマ名 DATAFILE
‘C:\app\Administrator\oradata\サービス名\スキーマ名.dbf’ SIZE 100M REUSE AUTOEXTEND ON
MINIMUM EXTENT 1M
DEFAULT STORAGE ( INITIAL 1M NEXT 1M MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 4096
PCTINCREASE 0) ;
DBFファイル削除方法
DBを運用しているとファイルサイズが肥大化し、DBFファイルを削除する必要がでてきます。
・DBFファイルと状態
select file_name,tablespace_name,status,online_status from dba_data_files;
・スキーマ削除
drop user スキーマ名 cascade;
・DBFファイルの状態をオフラインに変更
alter database datafile ‘C:\app\Administrator\oradata\インスタンス名\スキーマ名.DBF’ offline;
・DBFファイルの管理から削除
alter database datafile ‘C:\app\Administrator\oradata\インスタンス名\スキーマ名.DBF’ drop;
この時点でSELECTできなくなります。
・DBFファイル削除
drop tablespace スキーマ名 including contents CASCADE CONSTRAINTS;
この時点でDBFファイルが削除されていない場合は、オラクルサービスを停止し、ファイル削除する。
テーブル、インデックスのinitialの変更
alter index インデックス名 rebuild storage ( initial 1m );
alter table テーブル名 move storage(initial 1m);
Ubuntu Subversionの構築
Subversion:インストール
sudo apt-get install subversion subversion-tools libapache2-svn
sudo vim /etc/apache2/mods-enabled/dav_svn.conf
ファイルの一番下の行に以下を追加。 sudo apache2ctl restart http://【接続先名】/svn/【リポジトリ名】
DAV svn
SVNParentPath /home/svn
Apache2のSVN用公開ディレクトリを「/home/svn」に設定しているので、ディレクトリ作成。
sudo mkdir /home/svn/
cd /home/svn/
sudo svnadmin create 【リポジトリ名】
sudo chown -R www-data:www-data 【リポジトリ名】
Windows10のOSバージョンの取得について
C++、VBScriptでOSバージョンを取得するプログラムを開発していたが、
クライアント端末にWindows10が含まれることに既存ロジックへの調査を実施した。
結果、C++でOSバージョン(GetVersionEx関数)を取得するロジックに不備が発生した。
GetVersionEx関数をMSDNで調査したところ、Windows8以降サポートをしないようだ。
Windows10でGetVersionEx関数を実行すると6.2(Windows8の値)という結果だった。
期待値は10.0だった。
下記URLに詳細が記述されている。
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/windows/desktop/ms724451(v=vs.85).aspx
・OSバージョンについて
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms724832(v=vs.85).aspx?tduid=(a1b7f744eb2d79c3ecc49da86e748d85)(256380)(2459594)(TnL5HPStwNw-4sBXUfjeKWq7DCpiwLPKMA)()
マニフェストファイルを生成し、Windows10を定義することにより問題が改善されるようだが、
サポートされないことからGetFileVersionInfo関数で代替えする方法を検討している。
・参考URL
https://togarasi.wordpress.com/2015/07/04/win10-os-%E3%81%AE%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3/
ちなみにVBScriptのOS情報の取得方法は下記だが、問題なく10.0XXXが取得できる。
Set objWMIService = GetObject(“winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\cimv2″)
Set colOperatingSystems = objWMIService.ExecQuery(“Select * from Win32_OperatingSystem”)
Hyper-V Server 2012への接続するクライアントの追加
■準備
コマンドプロンプトを管理者権限で追加すること
hvremote.wsfをc:\tools配下にコピーしておくこと
winrmサービスを起動すること(たぶん実行されていないので、自動にしておくとよい)
続きを読む